ようこそ! 愛知県公立小中学校事務職員研究会のサイトへ
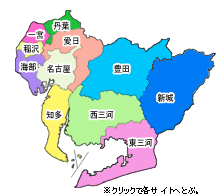
このサイトは、愛知県内の市町村立小中特別支援学校に勤務する学校事務職員で組織する「愛知県公立小中学校事務職員研究会」が公開・管理している情報サイトです。
私たち学校事務職員は、明日を担う子どもたちの豊かな成長を願い、子どもたちが安心して学び、安全に遊ぶことができ、楽しい思い出をつくることができる環境を提供したいと考えています。
そして、保護者や地域の願いに応えることができる、開かれた学校づくりを進めたいと願っています。私たちは、学校にいる唯一の行政職員として円滑な学校経営を担い、学校からの情報発信・収集を行いたいと思います。 -----[ ガイドライン ]
★会員の皆様へ、IDに関するお問い合わせは上部メニューのお問い合わせから送信願います。
2026.1.20 追加 睡眠改善コーチ・スリーピングマスター 三輪田理恵 様より、県大会後に実施したアンケートにおいて、全体会の内容に関して寄せられたご質問へのご回答を頂戴しましたので、掲載いたします。
※ 閲覧には、大会資料等と同じパスワードが必要になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
| ■目 的 | 「つなげよう 人と組織と地域を 子どもたちの未来へ」をテーマに、子どもたちの笑顔あふれる学校づくりを実現するため、地域・学校内での協働、新たな学校事務を創造し、具体的な実践を発信することで、学校事務職員の資質向上を図り、学校教育に寄与する。 | |
| ■主 催 | 愛知県公立小中学校事務職員研究会 | 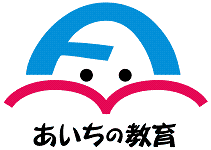 |
| ■共 催 | 愛知県教育委員会 | |
| ■後 援 | 愛知県都市教育長協議会・愛知県町村教育長協議会 愛知県小中学校長会 愛知県小中学校PTA連絡協議会 全国公立小中学校事務職員研究会 |
|
| ■期 日 | 令和7年11月11日(火) | |
| ■会 場 | 岡谷鋼機名古屋公会堂(名古屋市公会堂) | |
| ■講 演 会 |
テーマ 「睡眠でつくるメンタルタフネス -今日からできる働き方改革の実践-」 講 師 睡眠改善コーチ・スリーピングマスター 三輪田理恵 氏 |
|
| ■支部専門部発表会 |
【前半】 一宮支部担当 『自ら提案できる学校事務職員へ』 -気づきと協働で紡ぐ、校務運営参画の新たなステージ- 【後半】 知多支部担当 『 ちかづけ、めざす学校事務職員へ!たくさんの支援策で手厚くサポート!』 -PDCAサイクルで振りカエル知事研研究部の挑戦- |
|
| ■大 会 要 項 | ||
| ■申 込 方 法 | ||
| ■申 込 期 間 | 大会参加申込みは終了しています | |
| ■当 日 資 料 | 研究のまとめ(PDF) 支部発表【一宮支部】事前資料 支部発表【知多支部】事前資料 | |
| ■参 加 費 領 収 書 | ||
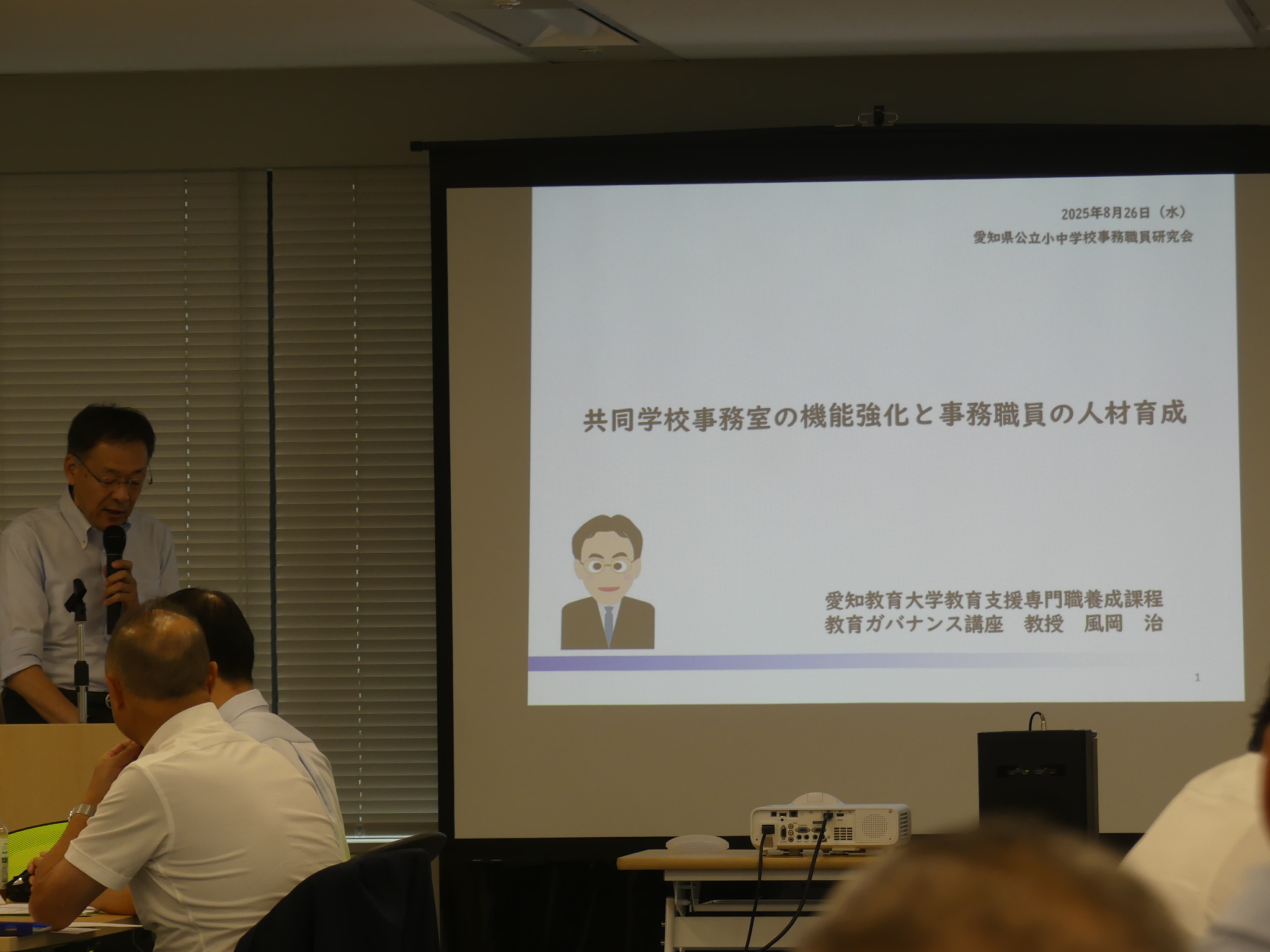 続いて、「共同学校事務室の機能強化と事務職員の人材育成」をテーマとして、愛知教育大学 教授 風岡治氏より講義をしていただきました。時代の流れの中で、事務職員にどのようなことが期待されてきたのか、その期待の中でこれまであげた成果と見えてきた課題について答申や調査結果等を踏まえて説明がありました。その後共同学校事務室・共同実施の役割の深化・機能強化について言及し、共同実施の原点は、学校の業務改善や経営改革等に大きなねらい・役割があり、役割を果たすことで子供・地域・保護者に効果を還元することが求められていると述べました。また、事務職員の連携・協働の場として機能することにより、人材育成の場としての効果も期待できると語られました。
続いて、「共同学校事務室の機能強化と事務職員の人材育成」をテーマとして、愛知教育大学 教授 風岡治氏より講義をしていただきました。時代の流れの中で、事務職員にどのようなことが期待されてきたのか、その期待の中でこれまであげた成果と見えてきた課題について答申や調査結果等を踏まえて説明がありました。その後共同学校事務室・共同実施の役割の深化・機能強化について言及し、共同実施の原点は、学校の業務改善や経営改革等に大きなねらい・役割があり、役割を果たすことで子供・地域・保護者に効果を還元することが求められていると述べました。また、事務職員の連携・協働の場として機能することにより、人材育成の場としての効果も期待できると語られました。 次に、「共同学校事務室の今とこれから」をテーマに、グループワークを行いました。実際の共同学校事務室でどのような取組を行っているのか、人材育成、事務処理の効率化・正確化などにおける今後について、学校事務職員が考えを述べた後、参加者それぞれの立場から、忌憚のない意見交換が行われました。「共同学校事務室と教頭会や校長会ともう少し連携や意見交換ができるとよい」「共同学校事務室には、評価がないことが内容の向上や拡大につながらない」などの意見が挙がっていました。グループワーク終了後に、風岡治氏よりまとめが行われ、学校事務職員の今後についてお話しいただきました。
次に、「共同学校事務室の今とこれから」をテーマに、グループワークを行いました。実際の共同学校事務室でどのような取組を行っているのか、人材育成、事務処理の効率化・正確化などにおける今後について、学校事務職員が考えを述べた後、参加者それぞれの立場から、忌憚のない意見交換が行われました。「共同学校事務室と教頭会や校長会ともう少し連携や意見交換ができるとよい」「共同学校事務室には、評価がないことが内容の向上や拡大につながらない」などの意見が挙がっていました。グループワーク終了後に、風岡治氏よりまとめが行われ、学校事務職員の今後についてお話しいただきました。
令和6年12月18日(水)愛知教弘研修室
 令和6年12月18日(水)、愛知教弘研修室において、愛知県内の各教育事務所次長兼総務課長・支所長代理、県校長会役員、県教頭会役員、市町村教育委員会職員、支部長、県事研役員の出席の下、学校事務情報交換会が開催されました。
令和6年12月18日(水)、愛知教弘研修室において、愛知県内の各教育事務所次長兼総務課長・支所長代理、県校長会役員、県教頭会役員、市町村教育委員会職員、支部長、県事研役員の出席の下、学校事務情報交換会が開催されました。
はじめに、県事研の事業内容について事務局長より紹介がありました。「あい・学校スマイルプラン」でミッションとして掲げた「教職員や地域の人々とともに子どもたちの笑顔あふれる学校づくりを進める」を達成するために展開する、組織・人・地域の「3つの柱」を軸とした「5つの戦略」について説明が行われました。続いて、「5つの戦略」の具体的な取組として共同学校事務室のモデル案について、研究開発部長より紹介がありました。組織的な校務運営への参画のための幾つかの取組のうち、稲沢市の共同学校事務室ブロックに協力していただいた「バーチャルな共同学校事務室」の取組について、参加者へ詳細な説明が行われました。
次に、「共同学校事務室の現状と課題について」をテーマに、瀬戸市と岡崎市の実践報告が行われました。それぞれの市において共同学校事務室長を務める県事研副会長2名が報告者となり、両市の共同学校事務室に求められている役割や共同学校事務室での人材育成などの取組、それらに関する課題点を参加者と共有しました。
その後、「共同学校事務室の現状と課題について~課題解決の方策を考える~」と題して、三つの課題についてグループワークが行われました。グループで簡単な自己紹介が行われた後、最初の課題「共同学校事務室における人材育成について」の話し合いが始まりました。配付資料の「令和6年度愛知県市町村立学校事務職員研修計画」を参照しながら、各市町村での若手事務職員への研修の現状や教員の研修体系との比較、各教育事務所や市町村教育委員会からの共同学校事務室への支援体制について、参加者間で意見交換が行われました。
 二つ目の課題「共同学校事務室を活用した校務運営参画について」では、配布資料の「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)」の別表第一と別表第二を参照しながら、主に別表第二に掲げられた業務について話し合われました。別表第二の業務について、各市町村での取り扱いや管理職の立場からの意見等がグループで共有されました。あるグループでは、別表第二の業務の危機管理に関連して、若手事務職員が職員会で避難訓練の経路の不備(防火シャッターを考慮していない点)を指摘した事例が紹介され、参加者からは「校務運営への参画が高いハードルだと思わなくてもよいのではないか。この事例のように、自らのもつ能力や情報を少し生かすだけで参画は行える」と意見が述べられました。
二つ目の課題「共同学校事務室を活用した校務運営参画について」では、配布資料の「事務職員の標準的な職務の明確化に係る学校管理規則参考例等の送付について(通知)」の別表第一と別表第二を参照しながら、主に別表第二に掲げられた業務について話し合われました。別表第二の業務について、各市町村での取り扱いや管理職の立場からの意見等がグループで共有されました。あるグループでは、別表第二の業務の危機管理に関連して、若手事務職員が職員会で避難訓練の経路の不備(防火シャッターを考慮していない点)を指摘した事例が紹介され、参加者からは「校務運営への参画が高いハードルだと思わなくてもよいのではないか。この事例のように、自らのもつ能力や情報を少し生かすだけで参画は行える」と意見が述べられました。
三つ目の課題「室長の能力や役割について」では、室長に必要な能力や室長へ求める役割について話し合われました。室長に必要な能力としては組織を動かすマネジメント能力や周りを巻き込むリーダーシップ、室長に求める役割として、共同学校事務室の長として市町村統一で業務改善に取り組むことや所属校の管理職に対する学校運営上の助言を行うことなどが挙げられました。
最後に、各グループの参加者で感想を述べ合った後、高浜市立翼小学校 校長 村越氏と、東三河教育事務所新城設楽支所 支所長代理 堀氏より、「組織的に参画に取り組むには、システム化が大切」「まず動き出し、そして改善する」「行政と学校、校長と事務職員、それぞれの立場の思いや動きをバラバラではなく集約すべき」などの講評をいただき、本会は閉会となりました。
令和6年11月20日(水)愛知教弘研修室
 令和6年11月20日(水)、坂種栄ビル10階の愛知教弘研修室において、令和6年度市町村代表者会が行われました。 教育事務所次長兼総務課長、市町教育委員会関係者などの来賓をはじめとして、多数の参加者がありました。また、オンラインでも20名余りの方にご参加いただきました。
令和6年11月20日(水)、坂種栄ビル10階の愛知教弘研修室において、令和6年度市町村代表者会が行われました。 教育事務所次長兼総務課長、市町教育委員会関係者などの来賓をはじめとして、多数の参加者がありました。また、オンラインでも20名余りの方にご参加いただきました。
はじめに、山敷会長による挨拶の後、愛知県教育委員会あいちの学び推進課 担当課長 三矢 克之氏より「コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進について」と題して、講演が行われました。講演の中で、コミュニティ・スクールの基礎的な知識の解説やご自身が勤めた公立小中学校で取り組まれた地域との連携・協働に関わる実践事例を紹介していただきました。まとめとして、「事務職員の皆さんも地域との連携・協働について当事者意識をもち、地域に開かれた学校づくり、学校を核とした地域づくりに対して、一緒に関わっていただきたい」とのお言葉で、講演が締めくくられました。
続いて、情報戦略部よりコミュニティ・スクール状況調査についての結果と分析報告が行われた後、『コミュニティ・スクールと学校事務職員の関わりについて』というテーマで、実践事例の紹介が行われました。蒲郡市立西浦小学校 総括事務長 小島 賢三氏からは「蒲郡市のコミュニティ・スクールの推進について」、豊橋市立磯辺小学校 主事 前澤真希子氏からは「豊橋市での事務職員の地域連携業務への関わりについて」、瀬戸市立長根小学校 主任 西尾 縁氏と瀬戸市立瀬戸特別支援学校光陵校舎 主任 松井 政徳氏からは「地域連携担当教職員としての事務職員のありかたについて」との題で、お話をしていただきました。教育委員会のコミュニティ・スクール担当者としての経験、学校運営協議会で実際に提案した協議内容、人事異動を挟んでも地域連携担当教職員としての役割を果たす仕組みづくりなど、貴重な実践の紹介をしていただきました。
最後に、各専門部局員による県事研の活動紹介並びに研究開発部による令和7年度東海大会に向けた研究経過の報告が行われました。

