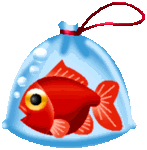
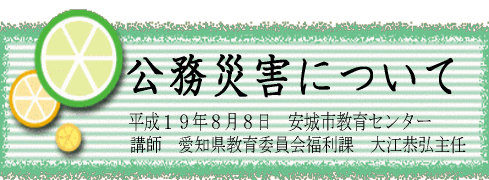
![]()
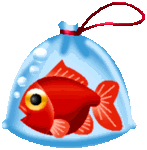
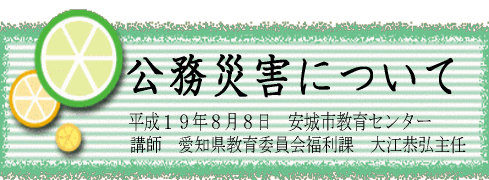
![]() 公務災害とは
公務災害とは
(1)制度の概要
使用者の無過失責任主義
・基本的に勤務中に負傷すれば公務災害。
例)教材作成中にカッターで手を負傷
授業に向かう階段で足をくじく
・県や国に過失がなくても補償を行う。
![]() しかし本人の過失が重大な場合は過失に応じた制限がある。
しかし本人の過失が重大な場合は過失に応じた制限がある。
身体上の損害のみの補償
例)顔の打撲に伴うメガネの損壊 → メガネ代は補償されない。
顔に傷がついた慰謝料(精神的な損害)も補償されない。
しかし、青あざは身体的な損害と認められる場合もある。
被災した職員が請求し、定型的・定立的な補償
・被災した職員が請求してはじめて成立する。
・法令に定められた一定水準の補償。(ただし治療費は全額補償。)
![]() 具体的な補償の種類
具体的な補償の種類
・治療費の全額補償
・障害が残ったときの補償
・死亡したときの遺族への補償
![]() その他、公務災害の服務上、給与上のメリット
その他、公務災害の服務上、給与上のメリット
・公務災害での休職は療養に必要な期間とることができる。
治ゆするまで何年でも身分が保障される。
(私傷病・通勤災害の休職は3年以内)
・公務災害での休職は給与が減額されることがない。
(私傷病の場合は減額)
(2)対象職員
対象となる職員
常勤職員・再任用職員・期限付任用職員・臨時的任用職員
対象とならない職員
非常勤職員、期限付でも臨時的な現業職員(期限付用務員・臨時的給食調理員)
→労働災害となるので最寄の労働基準局で申請。
![]() 対象職員でも、公社・協会等に出向している間は労働災害の扱いとなる。
対象職員でも、公社・協会等に出向している間は労働災害の扱いとなる。
(3)公務災害の認定基準
公務遂行性・・・職員が公務に従事し、任命権者の支配管理下にある状況で発生した災害であること。
○ 廊下で移動中のケガ、仕事前・仕事後の着替え、昼食をとるために近くの食堂に行く間等。
× 食事中・休憩中にテレビを見ている時等、私的な行為をしている場合。
![]() 教員が休憩時間中に児童と遊ぶことは職務の一環と考えられ、公務遂行性があるとされる。
教員が休憩時間中に児童と遊ぶことは職務の一環と考えられ、公務遂行性があるとされる。
公務起因性・・・公務と負傷・疾病との間に相当因果関係があること。
外傷は外見上公務起因性は明らか。
疾病(脳卒中・心臓疾患・腰痛・頚部痛等)の場合、持病が元でたまたま公務中に疾病がおこった
場合があるので、本人の基礎疾患を調査する。
![]() たとえば事務職員の場合、直前1月に100時間の残業等、明らかに過重な労働が原因で疾病
たとえば事務職員の場合、直前1月に100時間の残業等、明らかに過重な労働が原因で疾病
が起こったと判断されない限り公務起因性があるとされず、認定されない。
![]() 公務災害発生から事務処理が完結するまでの主な流れ
公務災害発生から事務処理が完結するまでの主な流れ
(1)公務災害が発生したとき
公災(通災)認定手続証明書
・公務災害を認定請求していることを病院側に認識してもらうための書類。
・提出は初診のときがベストだが、無理なら次回以降なるべく早く。
・初回に共済組合員証を使っても次回この証明書を出して、病院に初回分のお金を返してください
と言うと、たいていの病院は返してくれる。
病院によっては公務災害に認定されるまでの立替を依頼してくるが断ってほしい。
公務災害認定請求書
・原則被災職員が作成
・所属団体名は「愛知県教育委員会」と記入
・所属部局は「○○市立○○小学校」等と記入。
・共済組合員証・健康保険組合員証記号番号は「公立愛知 第 ○○○○○○(組合員証番号)」
(期限付き・臨時的任用は社会保険証の番号)
・災害発生状況写真又は図・現認証明書又は事実証明書・診断書・経過報告書は必ず添付すること。
・任命権者の意見は空欄に。
![]() 公務災害認定請求書は代筆が可能。
公務災害認定請求書は代筆が可能。
災害発生状況写真又は図
・災害が発生したときの状態が一目で分かるもの。
現認証明書
・現認者は職員である必要はないが、生徒は不可。
現認者が生徒しかいない場合、事実証明書を作成する。
事実証明書
・手引き(P163)にある事実証明書の「4災害発生の状況」に書いてある最後の4行は決まり
文句なので同じように記載してほしい。
・事実証明者は教頭以上の役職者が作成し、印は私印とすること。
診断書
・「疾病、整形用」の様式が昨年新たに作られた。疾病・整形事案で、病院の様式で診断書を
もらったとしても、取り直す必要はない。
経過報告書
・受診した病院の数だけ必要。共済組合員証等の使用の有無の欄は、当初から保険証を使用してい
たとしても、使用していないということにできないか病院に相談してほしい。
・複数の病院に受診したときは経過報告書とともに転医届が必要になる。
![]() 大半の公務災害は以上の5点(公務災害認定請求書、災害発生状況写真又は図、現認証明書又は事実証明書、
大半の公務災害は以上の5点(公務災害認定請求書、災害発生状況写真又は図、現認証明書又は事実証明書、
診断書、経過報告書)で認定される。難しいと思わずに事務にあたってほしい。
![]() 書類は市町教委→西三事務所→県教委福利課→公務災害基金の順で送られる。
書類は市町教委→西三事務所→県教委福利課→公務災害基金の順で送られる。
![]() 認定されるまでの期間は、簡易な事例なら不備さえなければ福利課に書類が届いてから1週間
認定されるまでの期間は、簡易な事例なら不備さえなければ福利課に書類が届いてから1週間
くらい。
(2)療養しているとき
公務災害として認定されると、公務災害基金から公務災害認定通知書が市町教委経由で
送られてくる。
![]() 受診した病院が指定医療機関の場合
受診した病院が指定医療機関の場合
療養の給付請求書
・これを1度提出すれば、あとは病院と基金の直接のやりとりとなる。
![]() 指定医療機関(手引きP203〜)
指定医療機関(手引きP203〜)
西三管内では岡崎市民病院、碧南市民病院、刈谷豊田総合病院、安城更生病院、西尾市民病院等。
![]() 受診した病院が指定医療機関ではない場合
受診した病院が指定医療機関ではない場合
療養補償請求書
・病院が公務災害基金に請求するたびに必要。コピーの使いまわしは不可。
・毎月1回は療養補償請求書を病院に持っていくように。
・院外処方の場合、薬局にも別に療養補償請求書を提出すること。
![]() はり、マッサージ、カイロプラクティックは自己負担となる。
はり、マッサージ、カイロプラクティックは自己負担となる。
(3)治ゆしたとき
治ゆ報告書
・通常の治ゆの場合、これを提出すれば公務災害事務は終了。
・症状固定の治ゆのときは障害の有無の欄を有にして、残存障害診断書等を添付すること。
・残存障害が障害等級にあたるとされた場合は事務所を通じて福利課から別途連絡が行く
ので指示に従う。
![]() 通勤災害
通勤災害
・通勤災害とは
通勤災害とは、通勤による災害、すなわち職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、
合理的な経路及び方法により行うことに起因する災害をいう。
(ア)住居と勤務場所との間の往復
(イ)複数就業者の就業の場所から勤務場所への移動
(ウ)単身赴任者の赴任先住居と帰省先住所間の移動
![]() 合理的な経路及び方法とは
合理的な経路及び方法とは
1 基本的には通勤届の経路上
この経路上の事故であれば飲酒運転等していない限りまず通勤災害と認められる。
2 通勤事情によるもの、通勤に伴う合理的必要行為
・経路上の道路工事等、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路
・事故、スト等の場合の代替輸送機関による経路
・自動車通勤の者がガソリン補給のためガソリンスタンドに立ち寄る経路
![]() 混雑状況の事情により日常的に行きと帰りの経路が違う場合も合理的な経路と判断
混雑状況の事情により日常的に行きと帰りの経路が違う場合も合理的な経路と判断
されるが、なぜその経路を利用しているかの申立書が必要となる。
経路から外れていたとしても、逸脱や中断が日常生活上必要な行為であって総務省令で
定めるものであれば、逸脱や中断の間に生じた災害を除き、通勤災害とされる。
![]() 日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるものとは
日常生活上必要な行為であって総務省令で定めるものとは
1 日用品の購入その他これに準ずる行為
・日用品に該当するもの…飲食料品、家庭用薬品、衣料品、文房具、書籍、子どもの玩具等
・日用品の購入に準ずる行為…理髪店や美容院に行く、市役所に戸籍謄本を取りにいく等
2 学校教育法1条に規定する学校において行われる教育等を受ける行為
3 病院において診察、治療をうけることその他これに準ずる行為
4 選挙権の行使その他これに準ずる行為
![]() 事例検討
事例検討
(1)部活指導中のケガ(土曜日の部活指導中に負傷。右手首の曲がりについて、症状固定の治ゆ。)
![]() 公務災害認定請求書に添付する書類で、手引きに書いてあるもの以外に必要な書類
公務災害認定請求書に添付する書類で、手引きに書いてあるもの以外に必要な書類
(公務災害が発生したことがより明らかになる証拠書類)
学校経営案の教職員名簿(部活動の担当がわかるもの)
休日の部活動計画書(土日に起こった災害なので)
・症状固定の治ゆなので、治ゆ報告書と残存障害診断書をあわせて提出
![]() 残存障害診断書から障害等級にあたるかどうかを基金が判断
残存障害診断書から障害等級にあたるかどうかを基金が判断
・障害等級にあたる場合・・・ 障害補償手続きへ
・障害等級にあたらない場合・・・ 公務災害事務はこれで終了
(2)通勤途上の交通事故(帰宅途中、赤信号を直進して右折車と衝突。目撃者なし。)
![]() 通勤災害認定請求書(災害発生状況写真又は図・事実証明書・診断書・経過報告書を添付)
通勤災害認定請求書(災害発生状況写真又は図・事実証明書・診断書・経過報告書を添付)
に加え、通勤災害で交通事故の場合に必要となる書類
交通事故証明書
・最寄の警察署、交番、農協等で申請用紙を入手し、郵送により又は直接自動車安全
運転センターへ申し込む。人身事故となっていることを確認する。
事故発生状況報告書
・被災職員が作成。速度欄に制限速度を括弧書きで記入すること。
・道路の幅をm(メートル)で記入する。
通勤届・通勤経路図
・通勤経路図は通勤届の裏側ではなくて、市販の地図やインターネットで入手した地図を
使用して作成する。自宅と勤務場所を○で囲む。距離が遠い場合は、縮小した地図を
継ぎはぎして作成。
![]() 例とは異なり、第三者加害事案になった場合に必要な書類
例とは異なり、第三者加害事案になった場合に必要な書類
第三者行為災害届
・相手からケガを受けたときに作成する書類。(交通事故、生徒から殴られた等)
加害者が小学生・・・第三者加害事案としない
加害者が中学生・・・第三者加害事案とする
![]() 民事裁判では12歳以下は責任能力がないとされていて、公務災害でもそれに
民事裁判では12歳以下は責任能力がないとされていて、公務災害でもそれに
準じている。
・損害賠償請求方法欄
示談先行・・・公務災害基金が治療費を先行して補償しない。
交通事故の場合は保険会社が、生徒からの加害の場合は保護者が先行して補償。
![]() 示談先行になるとき
示談先行になるとき
第三者に一方的な過失があるときや、治療費が自賠責保険の範囲(120万円)
に収まるとき等。(入院しない場合はよほどのことがない限り示談先行となる。)
補償先行・・・公務災害基金が治療費を先行して補償する。
治ゆした時点で相手方に求償する。(交渉は被災職員自らが行う。)
念書
・被災職員が作成。補償先行の場合必要。
確約書
・実際に損害賠償金を支払う者や任意保険会社の支店の代表者が記入。
補償先行の場合必要。
・第三者の同意が得られず確約書の作成が困難なときは福利課に相談する。
治ゆ後、示談を締結する前に示談書の案を基金に提出する。
示談を締結後、損害賠償受領報告書に示談書等の写しを添付して提出。
![]() 示談書は交通事故の場合、任意保険会社が作成した示談書を活用する。生徒からの
示談書は交通事故の場合、任意保険会社が作成した示談書を活用する。生徒からの
暴行事案のときは、手引きP190記載例を参考に作成してほしい。
![]() 研修時配布された公務災害についての質問と回答はこちら(ワードファイル)
研修時配布された公務災害についての質問と回答はこちら(ワードファイル)